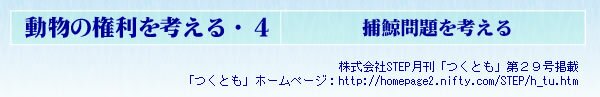
株式会社STEP(代表取締役:竹島茂氏)は、つくば市を地方の個性を豊かに生かした町にするために1985年から出版活動を行ない、今日に至っています。自然環境の悪化をくい止めるための活動の紹介や、地元の研究者による啓蒙書など、多くの出版物を世に送り出してきました。
この度、本会の会員がSTEPの特派員としてIWC会議に参加して、取材報告記事を書きました。
<<STEP特派員報告>> 辺見 栄
本会議開催中の5日間、STEPの記者として、会議の進行を取材してきましたが、以下に本会議で討議された内容を項目別にまとめて、その概略を報告します。 無記名投票案の採決 実際には、日本に追随する小国は、驚くほど活発に意見を述べており、数年にわたる日本政府の提案は、かなり政治的なものと思えます。採決を無記名投票にすれば、捕鯨支持国が増えると考えて、提案を続けているとのことです。 改定管理制度(RMS=Revised Management Scheme) しかし、多数の国が、このシステムには監視体制、違反者の罰則規定を織り込む必要があり、捕獲方法、海域の設定、捕鯨船に同乗して捕獲頭数などをチェックする国際監視員の経費負担、鯨肉の流通ルートの監視なども、同時に決めるべきだと考えています。 日本政府はこの制度を採択に持ちこむことで、サンクチュアリ(鯨類禁漁区)を撤廃し、モラトリアム(捕鯨一時停止)を解除させ、商業捕鯨を再開したいと願っています。しかし、RMSとサンクチュアリ(鯨類禁漁区)の撤廃を結び付けて考えることは筋違いであり、RMSの採択が直ちにモラトリアムの解除を意味するものでもなく、日本が提案したRMS自体も各国の同意を得るには、まだまだ不備であると判断されています。 RMSを可決するには全投票数の4分の3の同意票が必要とされますが、日本政府はRMS採用への採決を提案し、賛成23、反対29、棄権5で、日本の提案は否決されました。その結果、日本政府が今年望んでいた商業捕鯨再開への道はとざされ、この議題は来年以降に持ち越されました。 しかし、RMSの完成をめざして、必要に応じて閣僚レベルの会合を行なうことが、賛成25、反対3、棄権28で決まりました。 日本の沿岸小型捕鯨 私はIWCの会場へのバスの往復で、デンマークの代表としてグリーンランドから来ているIWC参加者と先住民捕鯨について話をする機会がありましたが、日本とグリーンランドとは全く事情が異なり、クジラ、イルカ、シロクマ、シャチ、ベルーガ(シロイルカ)、水鳥にいたるまでを食べなければ生存が危ういというグリーンランドの生存捕鯨を、日本の沿岸捕鯨と同一視すること自体が、まやかしの訴えであると確信しました。日本の沿岸捕鯨は、明らかに商業捕鯨であり、先住民捕鯨とは異質のものです。また、沿岸捕鯨は伝統文化というよりは経済活動であり、日本政府の言うように否定されれば人権問題に発展するような重要な伝統文化であるかどうかについても大変疑わしく思います。さらに、伝統文化はどんなものでもそのまま継承していかなければならないというのもおかしな話です。野生動物の捕殺を保護に変えて、時代の推移を博物館内で過去の遺物的伝統として伝えていくことも可能であり、実際にその方法をとっている国や地域も存在しています。 日本の調査捕鯨拡大計画 調査捕鯨とは 日本政府は、モラトリアム(捕鯨一時停止)の実施以後、1986年をもって捕鯨を中止し、翌1987年から科学調査を目的とすると称して捕鯨を開始し、現在に至っています。つまり、名称が変わっただけで、日本は途絶えることなく事実上捕鯨を続けていることになります。 科学調査を目的にする調査捕鯨はIWCに計画書をだして通告するだけで実施できることになっています。このため、日本政府は、毎年調査捕鯨を通告し、調査のためのミンククジラの捕獲頭数を当初の300頭(±10パーセントの幅をもたせ、上限330頭)からじりじり上げるいっぽう、さらにニタリクジラ、マッコウクジラ、イワシクジラを調査の捕獲対象に加えるなどして捕獲枠を増やし続けてきました。調査の海域もすでに南氷洋、北西太平洋、日本沿岸に拡大しています。こうして得られた鯨の肉は市場に出され、多額の収益をもたらしています。つまり、調査捕鯨は実質的には商業捕鯨と変わらないというのが現状です。 IWC会議では、これまでほとんど毎年のように日本の調査捕鯨に対して、クジラを殺さないで調査する非致死的な調査へ切り替えるか、調査捕鯨を中止するようにと勧告し、調査捕鯨への反対決議が採択されています。しかし、決議に拘束力がないため、日本は決議を無視し続けてきました。 拡大される第2期調査(JARPAⅡ)捕鯨の通告 こうして日本政府による南氷洋(南極海)での調査捕鯨は1987年以来18年間にわたって行われてきましたが、今年の3月をもってその調査が終了したため、日本政府は新たに第2期調査(JARPAⅡ)として南極海での調査捕鯨を大幅に拡大して行なうことを決め、これをIWCに通告しました。その内容は、
1)ミンククジラの捕獲数を倍増して、年間850頭にする。(±10%の幅をもたせることにしたため、上限935頭までの捕獲が可能)
2)大型種のナガスクジラ及びザトウクジラを捕獲対象にして年間各50頭を捕獲する。但し最初の2年間はナガスクジラの年間捕獲枠を10頭とし、ザトウクジラは捕獲しない。
3) この計画は6年後に見直しをする。
というものです。従来どおり、捕獲したクジラは胃の内容物などのデータを収集するなどして調査した後、その肉を販売し、収益を調査費に回すことにしています。 ザトウクジラもナガスクジラも過去の商業捕鯨で生息数が減少し、絶滅の恐れがあると考えられ、国際自然保護連合(ICUN)の絶滅危惧種リストに記載されています。いっぽう、ザトウクジラはホエールウオッチングの人気種です。オーストラリア周辺海域では回遊してくるザトウクジラのウオッチングが盛んで、南氷洋でのザトウクジラの捕殺が始まれば現行のホエールウオッチングが多大な影響を受けることが強く懸念されています。 第2期調査(JARPAⅡ)捕鯨への反対決議 しかし、それにもかかわらず、反対決議採決の直後、日本は決議を無視して南氷洋で拡大調査捕鯨を続けると宣言しました。南氷洋はすでに1994年にサンクチュアリ(鯨類禁漁区)としてすべてのクジラを手付かずの状態で次世代に残すことがIWC会議できめられている海域です。その海域で、日本はこれまで捕獲してきたミンククジラの捕獲数を倍増するだけでなく、大型種のクジラをも捕殺して調査し、その肉を利用すると宣言したのです。さらに、日本の水産庁次長は、反対決議案の採択を不服として、傲慢な態度で捕鯨に反対している国々を激しく非難するきわめて非紳士的で感情的な演説をはじめ、議長に制止されるという失態を演じました。 捕鯨全面禁止のサンクチュアリ(「聖域」、鯨類禁漁区) アルゼンチン、ブラジル、南アフリカが南大西洋にサンクチュアリを設定することを提案しましたが、4分の3の同意を得ることができず(賛成29、反対26、棄権2)この案は否決されました。いっぽう、日本は既存する南氷洋のサンクチュアリの取り消しを求める提案をしましたが、賛成25、反対30、棄権2で、4分の3の同意をとれず、この提案も否決されました。 日本、韓国、中国、ロシアによる共同目視調査の実施 このほか、本会議では、本会議の前に行なわれた科学委員会その他の委員会の報告や、それに対する意見交換があり、また、新設された「保護委員会」の運営の一環としてクジラと船舶との衝突問題、海中のソナーなどの騒音問題がとりあげられ、また、深刻な問題としてクジラ、特にコククジラが有害化学物質によってひどく汚染されている現状や、定置網にかかるなどのクジラの混獲問題も討議されました。 さらに、先住民捕鯨問題、クジラ捕殺についての致死時間やクジラの健康・福祉の問題、決議文の表現の修正など議論は広範囲にわたりました。 膠着状態のIWC会議 採決への投票の賛否は、捕鯨推進国と捕鯨反対国で、かなりはっきり分かれており、各国が賛否を発言する前に、どちらに投票するかがほとんど予測できる状態です。 重要法案を決議するには、全投票数の4分の3の賛成票が必要とされるいっぽう、まったく見解を異にする捕鯨推進国と反捕鯨国がほぼ同数であることから、本会議において重要なことは何も決まらないという膠着状態がここ数年続いています。このため、捕鯨推進国と反捕鯨国が互いに譲歩して議事を進行させるための折衷案が提議されましたが、両陣営の反対及び多数の棄権投票によって否決され、今回の会議でも、議論は平行線をたどったままで重要なことは採決には至りませんでした。 IWC会議における各国の立場 IWC開催国の韓国
しかし、商業捕鯨禁止によって捕鯨が中止されたことから、蔚山(ウルサン)は韓国第一の工業都市に変身しました。今では570万坪を超える自動車工場、船舶の建造所、重化学、パルプ工場など石油化学産業の工場が、深く内陸に切れ込んでいる蔚山港の両岸で365日昼夜を問わずフルタイムで生産を続けています。いっぽう、蔚山港の西岸の長生浦(ジャンセンポ)海岸には、今でも鯨料理を食べさせる食堂が残っています。韓国政府によると混獲によって入手された鯨肉は合法的に利用されているとの事です。しかし、デパートの食品売り場には鯨の肉は見られませんでした。
clear=all> IWC会議には捕鯨に反対する韓国のNGOも参加していて、捕鯨反対のちらしなどを資料として提供していましたが、会議の開催中、会場になったロッテホテルの前では、2回にわたって韓国人による捕鯨反対のデモが行なわれました。無作為に選んだ1000人の韓国人の意識調査によると、韓国では国民の21.7パーセントが捕鯨の再開に同意し、59.1パーセントの人が捕鯨の再開に反対という結果が出ています。また、かつての捕鯨基地であった長生浦でさえ、捕鯨の代替としてのホエールウオッチングに関心を寄せているということです。長生浦沖がコククジラの回遊域になっているからです。 clear=all> いっぽう、韓国政府が、経済的な理由から捕鯨再開を望んでいることは明らかですが、韓国の海洋水産相は、「鯨資源の持続的利用には賛成だが、商業捕鯨への賛否については明白でない」と発言し、採決に当たっては、日本の沿岸商業捕鯨再開には反対の立場をとり、また、日本が提案した重要事項であるRMSの採決や、南氷洋(南極海)サンクチュアリの廃止については棄権するなど、日本に協力しつつも日本に追随することなく独自の立場を保とうと努力しているようすがみられました。 clear=all> 韓国政府が捕鯨推進国としての立場をとり続けるかどうかは、今後の日本と韓国の関係によって決まってくるように思われます。この点、日韓、中国、ロシアによるミンククジラの目視調査の開始は、今後の韓国の姿勢にかなりの影響を与えるものと推測されます。 捕鯨に反対している国々 いっぽう、ホエールウオッチングをはじめ、クジラを保護してクジラと共存しながら収益を上げる方法や、IWCに新設された「保護委員会」を通してクジラの健康や福祉を考え、その生息数を健全に保つなど、時代の流れに合った方向へIWC会議を導くことを望んでいます。 日本及び商業捕鯨を望む捕鯨推進国 捕鯨推進大国、日本の拠りどころ そして、この調査捕鯨は、上記条約の「抜け穴」を日本があざとく利用して「合法的である」と主張しているものといえます。約半世紀前に、いったいだれが、またどの国が、科学の名の下にこれだけ多くの野生動物を犠牲にした史上に例を見ない調査が行なわれると予想したでしょうか? 日本の調査捕鯨結果は信用できるのか? しかし、科学委員会は、日本が出す調査結果はクジラを殺さない非致死的な調査でも得られるものであると、再三にわたって日本の調査を厳しく批判しています。また、日本が力を入れている食性生態調査 日本で一人歩きしている日本の「科学」 IWC会議の2日目に、RMSの採用に反対して、モナコの代表が「日本は10年間捕鯨再開に向けて努力しているが、それは日本の一人芝居だ」と発言したのが、大変印象的でした。日本の捕鯨再開への情熱は、本会議への政府筋の参加者の人数にも現れていて、今回の登録者数は約80人。「科学的な」資料として並べられる印刷物もダントツに豪華なカラー版で、その数も群を抜いており、捕鯨再開にかける意気込みを表していました。 しかし、それは同時にいかに鯨の肉で経済的に潤っているかを証明するものでした。 しかし、そうした豪華な資料とは裏腹に、IWC加盟国やオブザーバー参加のNGOのあいだには日本の科学に対する不信感が強く見られました。 日本が「科学的」調査の結果として提唱している「南氷洋に76万頭以上のミンククジラがいる」という説に対しても、IWC本会議で、実際の生息数はその半分だと科学委員会が考えているという発言がありました。実際には、それよりさらに少ないという説もあります。10年ほど前に、日本で捕鯨関係者と動物研究者、動物保護関係者が参加して、捕鯨問題について討論する会合が開かれたことがあります。その時、ニホンザルの研究を長年続けている学者が私に語った言葉が強く印象に残っています。その学者は日本政府の76万頭説に疑問を呈して、たまたま隣の席に座った私に次のように話したのです。 「北限の青森に棲む陸上の野生のサルの生息数でさえ確かなことが分からないのに、なぜ広大な南氷洋で絶えず移動しているクジラの生息数を断定できるのか?」 じつは、この「76万頭説」は、クジラが回遊する動物であることをまったく無視して、南極海の広大な海域を6つに分け、1982/83~1988/89の7年間、毎年末から年をまたいで1海区ずつ船を走らせてそこで目視したクジラの数を基に、多くの数字のからくり操作を施してひねり出した全く信用できないと思われる説なのです。【参照:佐久間淳子氏による「『ミンククジラは76万頭』説の実態を大解剖! しかし、日本ではこの76万頭説が一人歩きして、「76万頭」という数字はIWC委員会によって正しいと承認されている生息数であり、南氷洋には害になるほど多数のミンククジラが生息していると一般に考えられています。しかも新聞、テレビなどの報道関係者の中にさえ、これを信じている記者が多く見られます。 また、「クジラの数が増えたので魚が不足して漁師が不漁にあえぎ、生活が苦しくなっている。魚不足を解消するために増えすぎたクジラを殺さなければならない」いう説も、その単純さのゆえに分かりやすく、日本国内に浸透し始めています。しかし、この日本の説は、科学委員会の支持を得ていないものです。自然の仕組みは決してそんな単純なものではないことは、多くの学者が指摘するところであり、一般人でも、少し頭を働かせれば「何かおかしい」と気づくはずのものだといえます。 日本は鯨肉を手に入れるために、「科学」的根拠を求め、調査捕鯨で得た収益だけでなく、補助金まで出して、それを調査捕鯨につぎ込んできました。しかし、それによって日本が国際社会から得たものは「日本の科学」に対する敬意ではなく、日本の科学に対する不信感、さらに「時に科学を振りかざし、時に先住民捕鯨の権利を情緒的に訴える」外交交渉への違和感であるといえます。そこには、モナコに指摘されるまでもなく「欲と二人連れの科学」にとりつかれ、「一人芝居」を演じ続ける日本の姿、いくら演じても空回りするだけの空(むな)しい姿が見え隠れしています。 捕鯨をどう捕らえるか:私たちとクジラの関係 戦後の食料不足の時代には、クジラは重要な食糧源と考えられ、鯨肉が配給されて人々の飢えをしのぐ蛋白源とされました。しかし、戦後60年、日本国民のクジラへの認識は劇的な変化を遂げています。多くの人々にとってクジラは殺して食べるものではなく、海洋に生きる巨大な興味ある野生動物として認識されています。湾内に迷い込んだクジラの命を心配し、浜に乗り上げた座礁クジラを救助し、クジラやイルカに会うために、お金を支払って彼らが棲む場所へ出かけていくイルカ・クジラ・ウオッチングなど「新しい文化」が急速に日本に普及しています。日本で1988年に始まったホエールウオッチングは急速に発展し、これまでに少なくとも150万人を大幅に超える人々がウオッチングに参加していると試算されています。現在、北海道から沖縄に至る日本各地約30ヶ所でイルカ・クジラ・ウオッチングが採算に合う事業として営業されています。また、1998年時点でウオッチングのチケット代金として事業者に入った直接収入は4億7,734万4,200円と試算されています。(エリック・ホイト著「世界に広がるホエールウオッチング」IFAW刊 以上ではっきり言えることは、現在の日本で、人とクジラの関わりには、大きく分けて「食べる側」と「見る側」という2つの立場があるということです。 不平等な日本政府の対応策 しかし、「見る側」つまり将来有望な市場であるウオッチング関係の事業に対する援助はありません。それどころかIWC会議で、日本代表はホエールウオッチングに関する議題を削除することを提案しています。この不平等さは、納税者である「見る側」の人々が今後問題にしていくべき重要な点だと考えます。 IWCの今後の課題 条約は変えられる:IWC会議は時代に即して変わるべき しかし、現状のIWCの取り決めでは、日本は商業捕鯨を再開できなくても、それに匹敵する捕鯨を調査の名の下に何ら厳しい監視をされることなく行なうことができるのです。そして、この調査捕鯨は、日本が主張するように条約の「抜け穴」を利用した合法的なものといえます。しかし、その様な「抜け道」を許す条約自体に問題があるという指摘もできます。 さらに、条約が施行されて半世紀以上がたち、今、クジラたちは人間による捕獲だけでなく、有害化学物質や海洋汚染、ソナーなどによる海中騒音、船舶との衝突,混獲、漁業の乱獲、そして気候の変動など、かつて考えられなかったような脅威にさらされています。野生動物を商業利用の対象にすれば、必ず金儲けのために野生動物が搾取され、不正に乱獲されて絶滅の危機を迎えることは、これまでの歴史がすでに証明しています。そして、際限なく拡大される調査を謳った捕鯨も、また、野生動物を搾取し彼らの生存を危うくするものです。IWCは確かに捕鯨を目的とする国際的な討議の場ですが、そもそもその討議によってIWCは、人間に搾取されすぎて絶滅の危機を迎えたクジラを保護するために、モラトリアム(捕鯨一時停止)を設け、その性質を変えて今日に至っているものです。 現在、野生動物についての科学的な知識は半世紀前とは格段の違いがあります。また、さまざまな脅威にさらされて生きる野生動物を次世代に健全な形で残していくためには、それなりの努力と我慢(犠牲)が必要とされます。そのいっぽう、近年になって、人間の権利だけでなく、同じ地球という環境の中で生きる動物たちへの人間による一方的な搾取を見直し、動物にも生きる権利を認めようという動きが、ますます世界的な強まりを見せています。捕鯨取締条約は何があっても旧態依然のままの形で守りぬかなければならないものではなく、時代の流れに即して変化して当然のものであり、事実、IWCのあり方も時代やその環境に伴って変化してきました。今後のIWCの課題は、国際捕鯨取締条約を見直し、時代に即したIWC会議の運営を試みることではないかと思います。 停滞するIWC会議の打開策 今後、日本はODAと鯨肉で得た豊富な資金を使って日本の息のかかった加盟国を増やし続け、IWCでの採決に向けて投票数の確保に努めることは間違いありません。現に水産庁の次長は前述した長い非難演説の中で、「来年こそすべての捕鯨推進国が会議に出席して巻き返しをはかり、捕鯨問題の転換期にしてみせる」と強い口調で『捨てぜりふ』的な発言をしています。もちろん、捕鯨に反対する国々も同様に得票を稼ぐ政策をとるでしょう。こうしてIWC会議はますます政治的な取引の様相を強めていくと予想されます。しかし、どちらの側にしても全投票数の4分の3の得票を得ることは、至難の業だといえます。従って打開策がないままIWC本会議は、このままの状態がしばらく続くものと考えます。 クジラは誰のものか? しかし、そのいっぽう、その公海でクジラを捕獲している日本は、南極海のクジラは日本のものだと考えていることになります。 いったいクジラは誰のものなのでしょうか? 人間中心主義的な視点からいえば、常識的に見て公海におけるクジラは、全世界のものといえるでしょう。しかし、クジラは自由に回遊して世界の海に姿を現す野生動物です。たとえばザトウクジラはアラスカからハワイ、そして日本へと広範囲に回遊していることが分かっています。また、日本の調査捕鯨によって南極海のザトウクジラが捕殺されれば、オーストラリアのホエールウオッチングが打撃を受けると懸念されています。渡り鳥をどの国の所有物と決めることが難しいのと同様に、クジラがどの国に所有されているのかを決めることも、きわめて難しいことだといえます。今回のIWC本会議の開会直前に中国の学者が「鯨類の保護は特定国の問題ではなく、世界的課題だ」と発言しましたが、鯨の帰属についても同様のことがいえるのではないでしょうか。一言でいえば、「クジラは特定国に帰属するものではなく、限られた地球という環境に独立して棲む海の生き物である」ということになるでしょう。 こうした視点に立って捕鯨問題を考えることが必要であるように思います。 日本の多くの人々にとって、捕鯨問題は大きな関心事ではないように思われます。イルカやクジラの肉が汚染されているという事実も、たいした関心事ではなく、日本政府は徐々に鯨肉を学校給食に取り入れさせていっていますが、「それに対しての大きな反対や異論は起こっていない。日本国民や子供たちは鯨肉の給食を喜んでいる」と釧路市長が本会議のプレスルームで行なわれた記者会見で発表しています。 しかし、いっぽう、こうした日本での鯨肉や捕鯨への関心の薄さは、もはや鯨肉が日本政府が声高に主張するような日本の伝統食でもなく、捕鯨が日本の文化を代表する伝統文化でもないことを間接的に証明しているといえます。日本でのイルカを含めた鯨肉の消費割合は、豚肉の1パーセント程度、禽獣類(牛豚鶏肉)の消費量の0.5パーセントにも満たないものです。鯨の肉は、もはや日本国民が是が非でも食べなければならない食料ではなくなっていることは明らかです。 クジラと共存して収益を上げる経済活動であるウオッチングという新しい文化を無視した形で、鯨肉の利用と普及のみに力を注ぎ、漁業活動として批判の大きい捕鯨という経済活動と、地方食に過ぎない鯨食を「伝統文化」や「伝統食」に塗り替えようとしている日本政府の偏った政策は、大きく見直される必要があると考えます。また、いっぽう、捕鯨推進国の一員として日本に住む私たちは、クジラに関して、広くは野生動物に関して自分がどのような立場をとるのかということを一人一人深く考えておく必要があるように思います。クジラ問題は、私たちが日本で想像する以上に、世界の関心事であり、一国の野生生物への対応は、その国の文化度を示すものと考えられているからです。 海外へ出かける機会が増している今日、私たち日本人が海外でクジラ問題について問われる機会はますます増えていくように思います。
copyright 無断禁転載
文:STEP、辺見 栄 写真:ENC |

 第57回国際捕鯨委員会(IWC)年次総会が、韓国の南東岸の工業都市である蔚山(うるさん)で6月20日から24日まで開催されました。今年、IWCへは新たに9カ国の加盟があり、IWC加盟国は66カ国になりましたが、本会議は採決への投票権をもつ57カ国が参加して開催されました。
第57回国際捕鯨委員会(IWC)年次総会が、韓国の南東岸の工業都市である蔚山(うるさん)で6月20日から24日まで開催されました。今年、IWCへは新たに9カ国の加盟があり、IWC加盟国は66カ国になりましたが、本会議は採決への投票権をもつ57カ国が参加して開催されました。



 反捕鯨国としての中心的な存在は、ニュージーランド、オーストラリア、イギリス、アメリカ、ヨーロッパ各国、メキシコ、アルゼンチン、南アフリカなどです。これらの国々は、クジラを殺さない科学調査が可能であると考え、日本政府が調査捕鯨と称してクジラを捕殺して鯨肉で収益を上げていることに厳しい目を向け、日本は科学の名を借りて商業捕鯨を行なっているとみなしています。そして、このまま日本に商業捕鯨を認めることになれば、クジラは絶滅しかねないと危惧し、基本的に日本にはクジラを捕殺することを認めない方針をとっています。
反捕鯨国としての中心的な存在は、ニュージーランド、オーストラリア、イギリス、アメリカ、ヨーロッパ各国、メキシコ、アルゼンチン、南アフリカなどです。これらの国々は、クジラを殺さない科学調査が可能であると考え、日本政府が調査捕鯨と称してクジラを捕殺して鯨肉で収益を上げていることに厳しい目を向け、日本は科学の名を借りて商業捕鯨を行なっているとみなしています。そして、このまま日本に商業捕鯨を認めることになれば、クジラは絶滅しかねないと危惧し、基本的に日本にはクジラを捕殺することを認めない方針をとっています。 DVD「日本のイルカ猟」
DVD「日本のイルカ猟」